こんにちは。
アトピー研究家の齋藤です。
夏になると、熱中症対策のために塩分を摂ることが勧められています。
それでは、熱中症対策のために、塩分は必要なのでしょうか?
このページでは「熱中症対策に塩分は必要なの?」という質問にお答えしていきます。
熱中症対策に塩分が必要と思えない理由
この記事を書いた理由は、私は塩分を意識的に摂っていないのに、脱水症状や熱中症になった事がないからです。
高校生の時は陸上部でしたが、陸上部の人は誰も塩分を摂らずに、水だけを飲んでいましたが、熱中症になった人はいませんでした。
その頃は、熱中症対策に塩分が必要と言われていなかった時代ですので、喉が渇けば水だけを飲むのが当たり前だったのです。
また、私が知る限り、部活をしている人で熱中症になっている人を見たことがありません。
炎天下で長時間運動をしているにも関わらず、塩を摂っていないのに、誰も熱中症にならなかったのです。
また、私は夏の炎天下に登山をすることがありますが、いつも塩分を摂らずに、喉が渇いた時は、お茶だけを飲んでいますが、熱中症になることはありません。
汗かきの体質のため、服が乾くと、汗から出た塩分が服に白くなって付いているほどですので、大量の塩分が汗で排泄されている事は間違いありません。
それでも、脱水症状や熱中症になったことはないのです。
そこで、疑問がでてきました。
汗で体内の塩分が排泄されるから、塩分を摂った方がいいという考えは、あまりにも短絡的過ぎるのではと思ったからです。
理由もなしに、塩分が汗から排泄されているとは考えにくいです。
体温を下げるために、塩分が邪魔になるから、汗から一緒に排泄されているはずです。
「汗から排泄しているということは、必要がない成分のはずなのに、塩分を摂るというのは、おかしいのでは?」と思ったのがこの記事を書いた理由になります。
なぜ熱中症対策に塩分が必要と言われているの?
熱中症対策に塩分が必要と言われていますが、そもそもなぜ、熱中症対策に塩分が必要と言われているのでしょうか?
その理由を調べてみました。
汗をかくと、水分と共に塩分が体内から失われます。
その時に、水分ばかりを摂ると、血液のナトリウムの濃度が下がります。
すると、血液のナトリウム濃度を一定に保つために、水分を尿で排泄するようになります。
その結果、脱水症状になり、その状態が続くと、熱中症になると言われています。

水分を飲み続ければ、脱水症状は回避できるの?
脱水症状の症状は、口の渇きや身体のだるさなどがあります。
ただ、脱水症状の症状があれば、水分を飲み続ければ、脱水症状は回避できます。
ほとんどの方は、喉が渇けば水を飲みますので、普通に生活をしていても、脱水症状にはならないのです。
それでは、どのような時に脱水症状になるのかと言えば、身体が水分を受け付けず、水分を飲むことができない時に、脱水症状が起こるのです。
これは、ご飯だけ食べても、あまり食は進まないのと似ています。
しかし、漬物や梅干しをご飯と一緒に食べると、漬物や梅干しに含まれている「塩分」が食欲を増進させるので、どんどんとご飯が食べられるようになります。
これと同じで、水を飲むことができなくても、少し塩を入れると、どんどんと水が飲みたくなります。
そのため、脱水症状や熱中症対策に、塩分を摂ることが大切と言われているのです。
なぜ汗から水分と一緒に塩分が排泄されるの?
汗から水分と塩分が排泄されるため、塩分を摂ることが推奨されていますが、そもそも、なぜ、汗から塩分が排泄されるのでしょうか?
塩分を体外に排泄することで、脱水症状や熱中症になるのなら、人体の機能として、汗から水分だけを排泄すればいいのではないでしょうか?
人間の身体は、わざわざ人体が危険な状態になるようなことをしません。
汗からでる成分に関しても、人体を守るために、排泄しているはずなのです。
それでは、なぜ汗から塩分が排泄されるのでしょうか?
これは塩の作用を調べると分かります。
それでは、塩分にはどのような作用があるのでしょう?
東北地方の人は塩分の摂取量が多いですが、塩分の摂取量が多い理由は、東北地方の冬はかなり寒いため、塩分で体温を上げるためと言われています。
つまり、塩分には体温を上げる作用があるのです。
寒い時に塩分が多い物を食べたくなるのは、体温を上げるためだったのです。
それでは、なぜ、汗から水分と一緒に塩分が排泄されるのでしょうか?
これは、何のために汗を出しているのかを考えると分かります。
塩分濃度が多いと体温が高くなるという事は、塩分を汗と一緒に排泄している理由は、体温を調節するためです。
汗から塩分がでると言っても、常に塩分が大量に含まれている訳ではありません。
体内の塩分濃度が低い時は、大量に汗をかいても、ほとんどが水分という事も良くあります。
このことから、塩分濃度が高いと体温がなかなか下がらなくなるため、汗で塩分濃度を調整している事が分かります。
身体に必要な塩分までは排泄されていないため、「余分な塩分」を汗と一緒に排泄しているのです。
つまり、汗から水分と一緒に塩分が排泄されるのは、体温調節をするためなのです。
南国の人は塩分が多いものを食べているの?
脱水症状や熱中症対策のために、塩分が必要な場合、赤道付近に住んでいる人は、塩分をしっかり摂っているのでしょうか?
赤道付近は常夏ですので、年中、暑い日が続いています。
調べてみたところ、アジアは比較的、塩分摂取量が多いのですが、これは、お米が塩と合うからだと考えられます。
お米は塩分を排泄する作用のあるカリウムが多く含まれていますので、アジアの地域で塩分摂取量が多いのは、仕方のないことかもしれません。
そのため、他の暑い地域の情報を調べてみると、南米や南アフリカは塩分の摂取量は少なく、エジプトやアラブ地方もそれほど多くありません。
もし、脱水症状や熱中症対策に塩分が必要な場合、赤道付近など、紫外線が強く、気温が高い国では、身体を守るために、昔から塩分を多く摂っているはずですが、実際の所はそうではないのです。
それでは、南国の人々は何を多く食べているのでしょうか?
日本と比較すると、果物の摂取量が非常に多いです。
台湾に旅行に行った時は、現地の人に、フルーツの屋台に連れて行ってもらったこともある位です。
また、私は東南アジアの国々を旅行で訪れていますが、現地の人は果物をよく食べていました。
東南アジアは屋台が非常に多いですが、果物の屋台もたくさんあり、賑わっています。
もちろん、東南アジアだけではありません。
ハワイも果物が多かったですし、私が何度も読んだ旅行記の「深夜特急」(沢木耕太郎著)では、アラブ地方の章では果物がたくさん登場していますので、アラブ地方の国々でも、フルーツが現地の人によく食べられているみたいです。
寒い時に、果物を食べようとは思いませんが、暑いときは果物をたくさん食べたくなります。
現在はエアコンの普及によって、状況が変化してきていますが、日本でも夏は「スイカ」がよく食べられていましたし、南国など暑い国では、果物がよく食べられている場合が多いのです。
それでは、果物に多い成分には何があるのでしょう?
代表的なものに「カリウム」があります。
カリウムはほぼすべての果物に含まれています。
それでは、その「カリウム」にはどのような作用があるのでしょう?
カリウムは、ナトリウムとペアで働くミネラルです。
そして、腎臓ではナトリウムの再吸収を抑制し、尿中への排泄を促進する働きがあるのです。
一言で言えば、カリウムはナトリウムを排泄する働きがあるのです。
ちなみに、私はフルーツ断食を3回行ったことがあります。
フルーツ断食とは断食の一種で、期間中はフルーツ以外のものは一切食べない断食の事です。
最高で20日間行いましたが、最後の方は口の中がしょっぱくなりました。
これは、ナトリウムが尿の中だけではなく、唾液からも排泄されるようになったからです。
また、フルーツばかり食べていると、身体がどんどんと冷えていきます。
これは、カリウムには体温を下げる働きがあるからです。
この働きを考えると、南国の人がカリウムの多いフルーツをよく食べるのは、日本人が夏にスイカを食べるのと同じで、体温を下げるためなのです。
まとめ
汗の成分ですが、含まれているのは塩分だけではありません。
カリウムなどのミネラルも含まれています。
この事から考えると、汗は、ただ単に塩分を排泄しているのではなく、ナトリウムとカリウムの調整をしている可能性が高いです。
しかし、カリウムの事はほとんど触れることがなく、塩分だけが強調されているのは、日本人の場合は、塩分摂取量が多いため、汗で必要がない塩分を排泄しているからだと考えられます。
人体は体温を上げる塩分を汗で排泄することで、体温を下げているのです。
それでは、なぜ、南国の人がカリウムが多い果物を良く食べるのか?
これは、東北の人々が寒いときに塩分を多く摂るのと同じように、暑いときに、カリウムを多く含む果物を取ることで体温調整をしているからです。
南国の人が熱中症対策のために、塩分を摂っている例は聞いたことがありません。
南国の人にとっての熱中症対策は、カリウムを摂ることなのです。
日本人は食事で塩分摂取量が多いため、汗から塩分が多く排泄されます。
しかし、果物ばかりを食べていれば、体内の塩分が激減しているため、汗をかいても塩分は排泄されないはずです。
実際、カリウムの多い食事をしていると、汗をかいてもベタつくことがなく、汗の成分のほとんどが水分の場合もよくあります。
また、塩分を摂ることを推奨している記事に、塩分が体温を上げる事を説明しているところは1つもありません。
これは、塩分が体温を上げるという塩分の作用を説明すると、熱中症対策に塩分を摂るという説明が矛盾してしまうからかもしれません。
もしかして、暑いときに塩分を摂ると、体温が上がることによって、逆に熱中症になってしまうリスクを認識しているため、塩分の作用について書いていないのかもしれません。
エアコンがない昭和時代は日本では暑いときはスイカを食べることで身体を冷やしていました。
南国のフルーツ摂取と同じで、スイカは昭和時代の熱中症対策だったのです。
昭和時代は塩分ではなく、カリウムを摂ることで熱中症対策をしていたのです。
確かに、汗から塩分が排泄されるから、塩分を摂ることが大切と言われると、もっともらしいように聞こえます。
しかし、南国の人が昔から食べているフルーツや、昭和時代のスイカのように、体温を下げるカリウムを摂ることの方が、熱中症対策としては理にかなっています。
また、健康な方は、体内の水分量が低下すると、喉が渇きます。
そのため、水分を摂取するため、脱水症状になることはありません。
そして、体内の塩分濃度の低下に関しても、ほとんどの日本人は塩分過多のため、余分な塩分が汗で排泄されることで、適正な塩分濃度になる場合がほとんどだと考えられます。
体内の塩分濃度が低い場合、汗を触ってもベトつかない事から分かるように、汗で塩分が排泄されることはほとんどなく、汗の成分の大部分は水分になるからです。
このことから分かるように、汗は体内の塩分濃度が低い場合でも、強制的に塩分を排泄しているのではなく、多すぎる塩分を排泄しているだけなのです。
まとめると、汗は余分な塩分を排泄しているだけですので、身体の機能維持に必要な塩分までは汗で流してしまうことはありません。
健康な方は、熱中症対策に体温を上げる塩分を摂るよりも、昭和時代にスイカを食べていたように、体温を下げる作用のあるカリウムの多い食べ物を食べることが熱中症対策にはお勧めです。
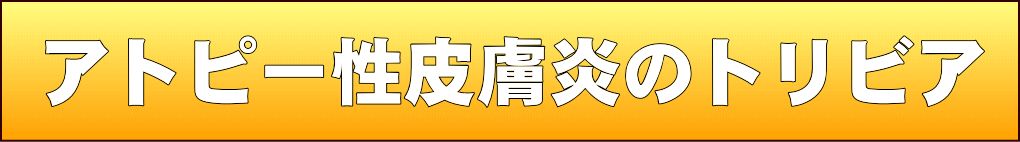
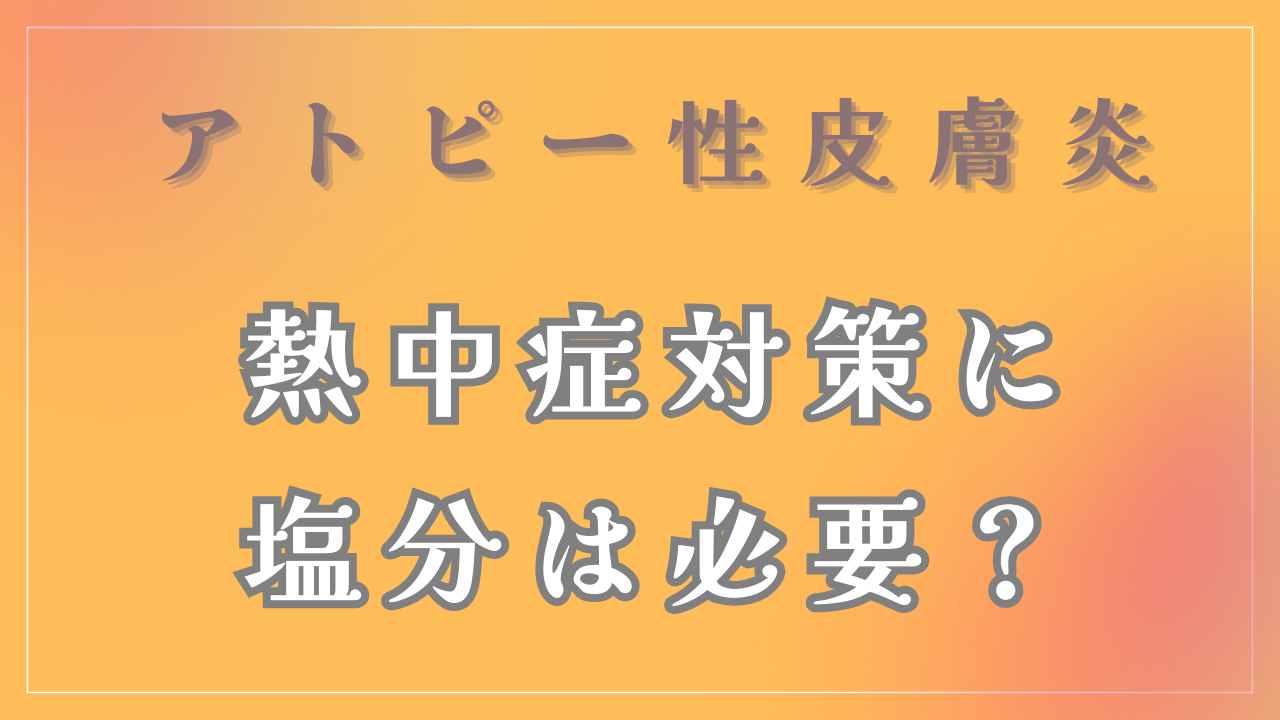
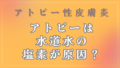
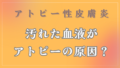
コメント